「なんか疲れてるかも…」が口ぐせになってませんか?
夏って、終わる頃に一気に疲れが出てきませんか?
身体は重いし、集中力は続かないし、なんとなく心もカラッカラ。
でもね、これってあなただけじゃないんですよ。
特にプレイヤー兼経営者やフリーランスみたいな“全部自分でやるスタイル”の人って、一気に反動が来やすい時期なんです。
「あれ、最近モチベが湧かんぞ…」
「気合いだけじゃ立ち直れんぞ…」
そんなとき、“気持ちを回復させる行動”を仕組みにできたら最強ですよね。
疲れを感じにくい人ほど、あとでガクッとくる
これはよく言われてることなんですけど、「頑張り屋の人ほど、疲れに気づくのが遅い」んです。
心理学者ロイ・バウマイスターの「意思決定疲れ(Decision Fatigue)」という概念、ご存じですか?
一日に何度も決断をすることで、精神的なリソースがどんどん削られていく現象です。
経営者って、常に「どうするか」を考えてますよね。
休みの日すら「次のキャンペーンどうしよう」とか、仕事のことが頭に浮かぶ。
つまり、脳みそが24時間営業してるようなもんです。
そら疲れますよ…笑
行動科学(ABA)で見る「疲労回復の習慣化」
さて、ここで行動分析学の出番です。
ABA(Applied Behavior Analysis)では、人の行動を「三項随伴性」という流れで捉えます。
- 先行刺激(きっかけ)
- 行動(やったこと)
- 結果(得られたもの)
この流れを上手に設計すると、回復行動が“勝手に”続く仕組みを作れるんです。
すぐ使える!メンタルを回復するための3つの行動設計術
1:先行刺激をセットする「気づきポイント」を仕込む
疲れって、自覚しにくいんですよね。
だから、「自分が疲れてるサイン」に気づけるようなルールや行動トリガーを設定しておきましょう。
- 朝、寝起きに重いと感じたら → “休息優先”ルール
- 食欲が落ちてたら → “15分だけ昼寝”ルール
この“感覚の変化”をきっかけに、決まったリカバリー行動をセットしておくのがコツです。
2:行動に即“ごほうび”を用意する
行動科学では、良い結果(強化子)があると人は行動を繰り返します。
たとえば:
- ストレッチ10分できた → 好きなコーヒーを飲む
- 21時以降スマホを触らずに寝た → 翌朝にお気に入りの音楽で起きる
「ちょっとやったら、ちょっといいことある」
この設計を日常に入れると、自然と“回復行動”が続いていきます。
3:行動のルーティンを「見える化」しておく
疲れてると、次に何すればいいかわからなくなるんですよね。
だから、“迷わなくて済む仕組み”を用意しておくと最強です。
たとえば、こんなチェックリスト:
- 朝:白湯を飲む → 5分深呼吸 → タスクを書き出す
- 夜:ストレッチ → 軽く日記 → 30分読書
このように、決まった順番でやることがあると“安心”できるんですよ。
脳にかかる負荷も減るので、まさにメンタルの回復装置になります。
疲れてるときほど「頑張らない仕組み」が必要なんやと思う
ついつい「気合いで乗り切ろう!」ってなりがちだけど、実はそれって回復とは逆の発想なんですよね。
疲れてるときこそ、「自分の行動を設計する」。
しかも、“脳が疲れててもできるレベルの行動”を。
最後に:疲れたら、回復を“習慣化”しよう
夏の疲れって、放っておくと秋バテ・冬バテにつながります。
そしてそれは、売上にも、判断にも、チームにも影響してくる。
だからこそ、疲れを見過ごさないで、“意図的な回復習慣”を生活に組み込むことが大切。
「疲れてるときこそ、優しく。仕組みで整える。」
それが、自分にも、仕事にも、ちゃんと還元される最短ルートかもしれません。


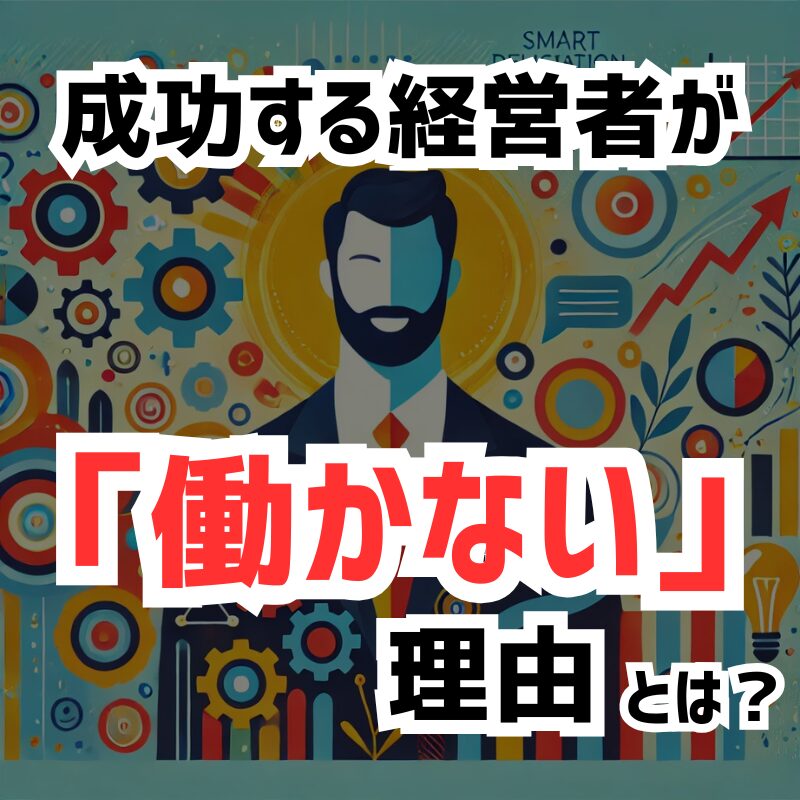

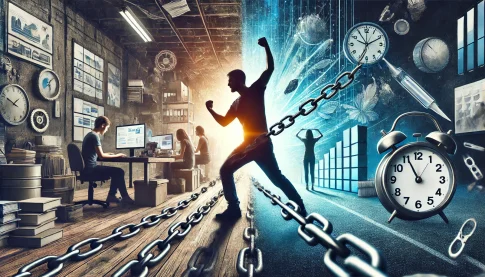

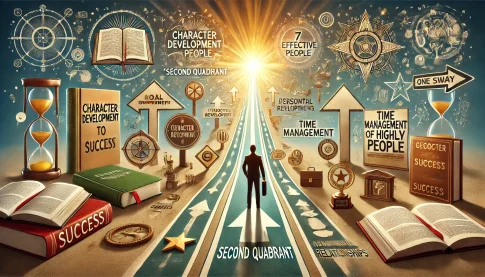


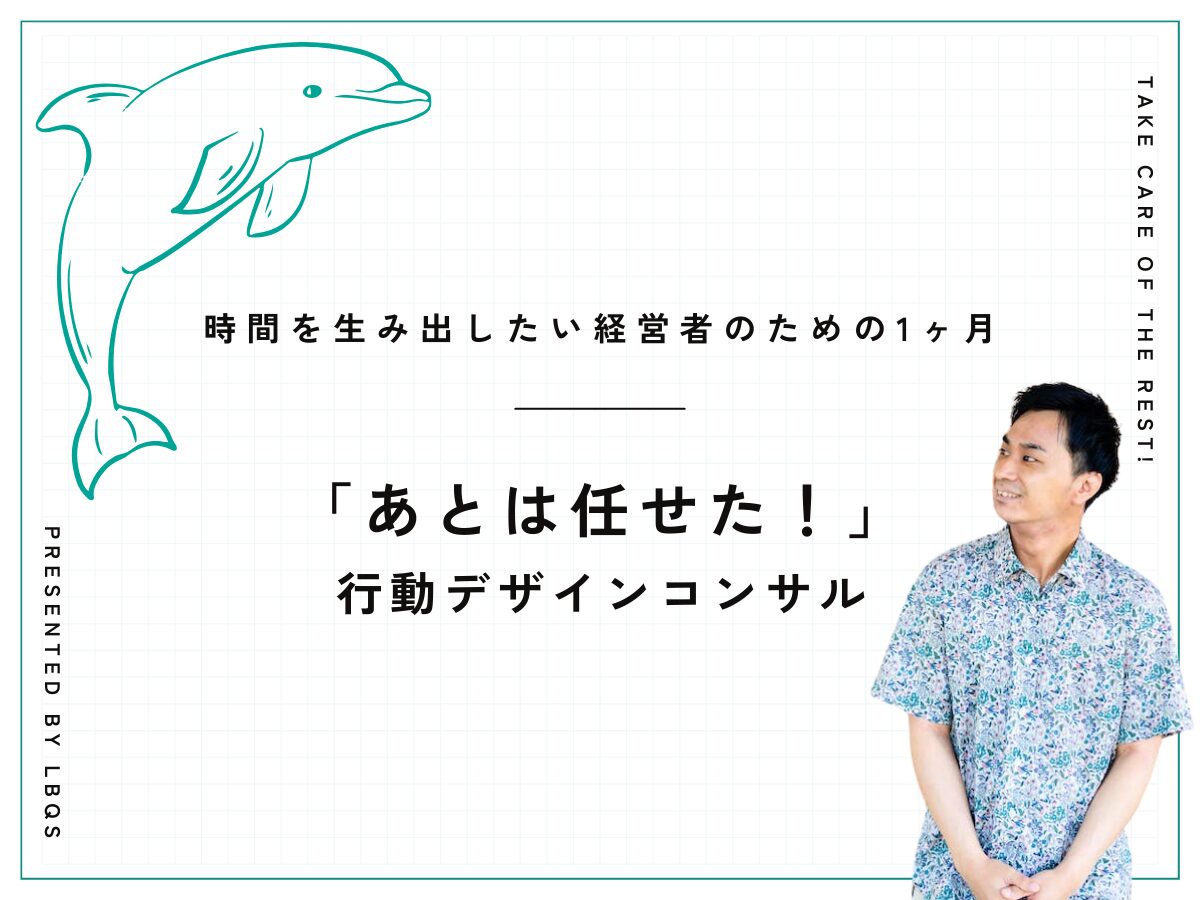
元イルカの調教師で、応用行動分析学を使った行動デザインコンサルタントの櫻井 祐弥です。