「最近の若い子は…」と言う前に、ちょっと立ち止まって考えてみませんか?
「うちの新人、ちょっと頼りないかも…」
「言ったことはやるけど、自発的じゃないんよなぁ…」
「急に来なくなったって、どういうこと?」
そんな経験、あなたの周りでも起きていませんか?
教えることは山ほどあるし、自分の仕事もパンパン。
ついつい「これはこうしてね」と、業務のレクチャーだけで精一杯になってしまう。
でもね、ふと思ったんです。
「育成の問題って、ほんまに“やり方”だけの話なんかな?」って。
成功する人に共通するのは、教え方じゃなく“継続できる環境”
アメリカの心理学者アンジェラ・リー・ダックワースが提唱した「GRIT(やり抜く力)」って聞いたことありますか?
彼女の研究では、「才能よりも、やり抜く力こそが成功を決める」とされています。
つまり、どれだけ優秀でも続かないと意味がないってこと。
これ、育成にもそのまま当てはまるなと思ったんです。
「仕事ができるか」よりも、「心が折れずに続けられるか」が大事なんやなって。
行動科学(ABA)で見る“心が折れる瞬間”とは?
行動分析学では、行動がどうやって生まれて、どう維持されるかを「三項随伴性(先行刺激→行動→結果)」で捉えます。
新人が辞める背景には、こんなパターンが多くあります:
- 先行刺激:「わからないけど聞きにくい雰囲気」
- 行動:「とりあえずやってみる(ミスする)」
- 結果:「注意される/責められる」→自信喪失、行動減少
この流れ、怖いですよね…。
悪気はなくても、「話しかけづらい上司」や「忙しい雰囲気」が無言のプレッシャーになってることも。
つまり、新人のメンタルが削られるのって、“人間関係”や“空気”といった環境要因に強く影響されてるんです。
モヤっとを減らす環境づくり。まずできる3つのこと
じゃあ、どうすれば新人が安心して育つ環境になるのか。
行動科学とコーチングの視点から、すぐにできる3つのステップを紹介します
1:先行刺激を変える=「安心の合図」を設置する
「わからないことがあれば聞いてね〜」ではなく、具体的な時間・場所・方法をセットで伝える。
例:「毎朝10分だけ“何でも相談タイム”取るね。SlackでもOK!」
2:行動にすぐ反応する=「小さな成功」に反応
ちょっとした進捗にも「いいね、それ」と反応して、ポジティブな結果を意識的に返す。
例:「さっきの報告、わかりやすかったよ。助かった!」
→強化子(行動を増やす結果)として働く。
3:曖昧さを減らす=ルーティンを明確に
新人の不安の元は“わからなさ”。
「何をすればいいか」をルーティン化して、考えるエネルギーを減らすのも効果的です。
例:「午前は〇〇のチェック。午後は△△の入力作業って感じで進めてね!」
「教えること」より「守ること」が先かも。
「最近の新人はメンタルが弱い」と言われがちだけど、実は**“仕組みの未整備”が原因**だったりします。
ルールが曖昧、声をかけにくい、達成感が薄い…
これじゃあ、続けろって言ってもキツイですよね笑
だからこそ、まずは環境を“行動が続く設計”に見直すことが大切。
最後にひとこと。
人は、安心できる環境でこそ、自分の力を発揮できます。
「教え方に悩む前に、“育てる場”を整えてみる。」
これが実は、一番のメンタルケアかもしれません。
試せそうなところから、ぜひちょっとずつ導入してみてくださいね。


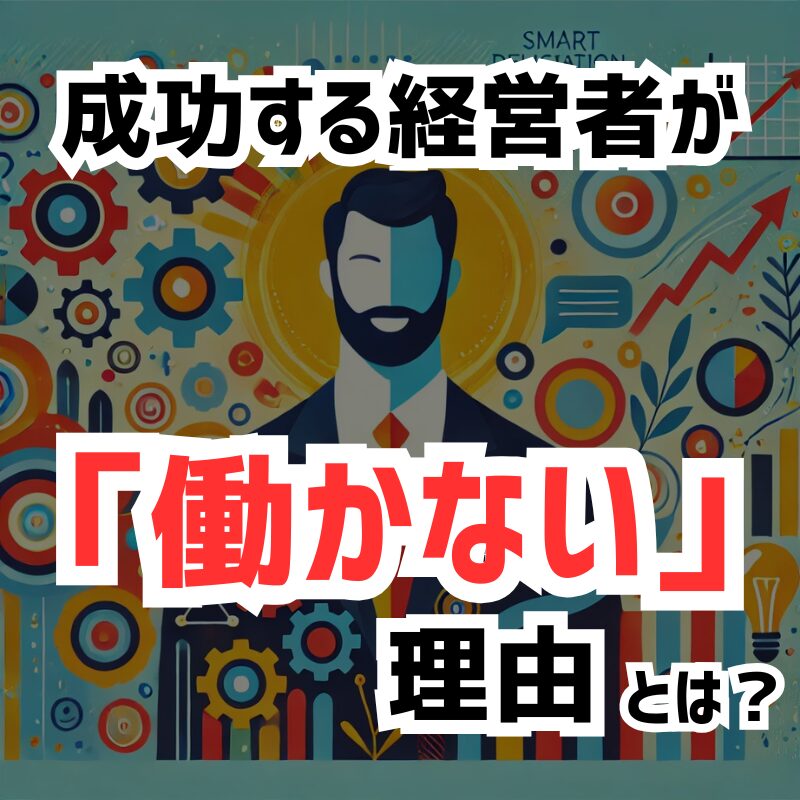





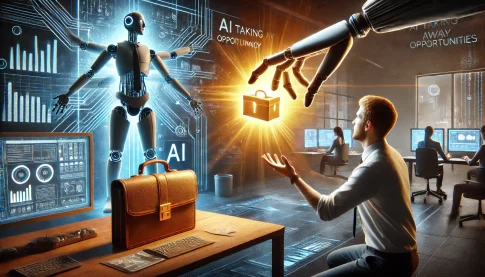



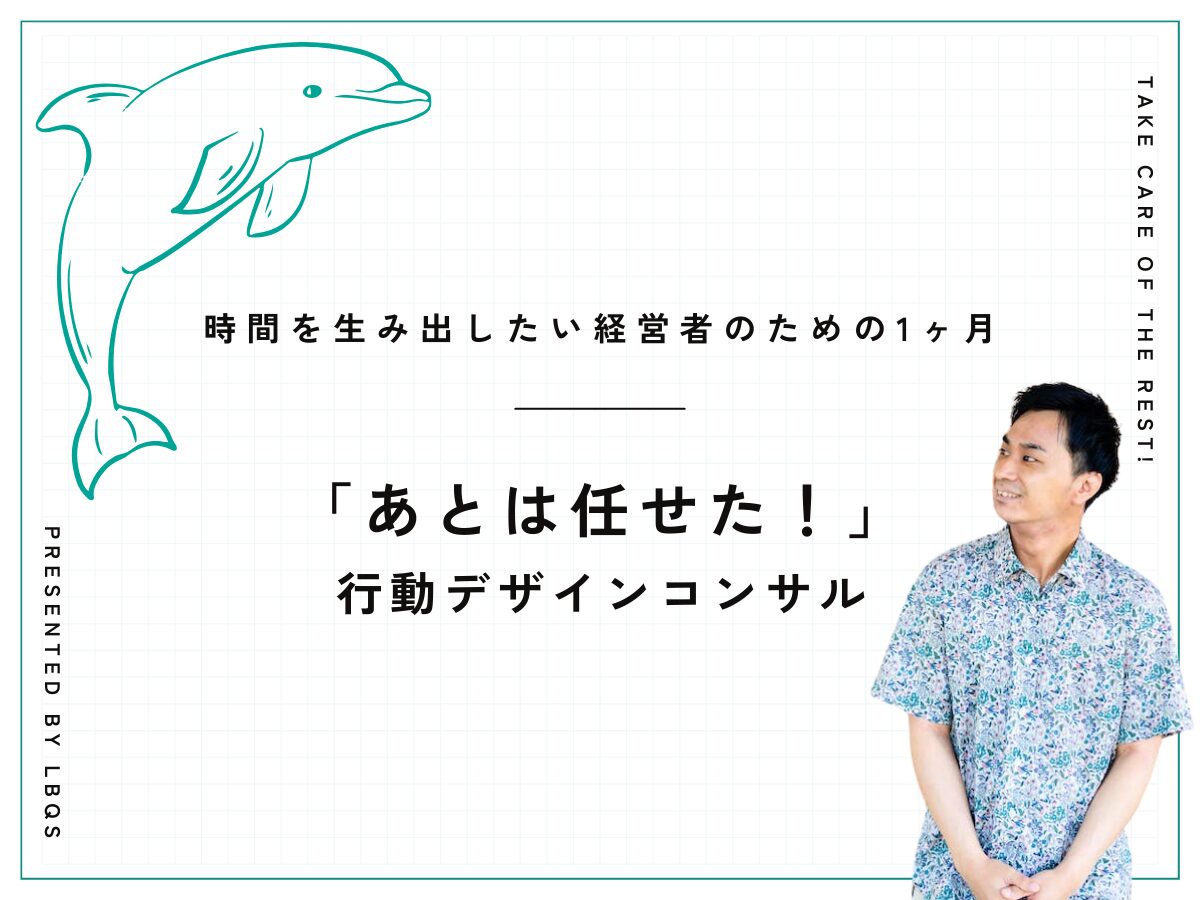
元イルカの調教師で、応用行動分析学を使った行動デザインコンサルタントの櫻井 祐弥です。