今回の記事は「最近、続かへん人が多いな…」と思ったら読むやつです。
「せっかく採用してもすぐ辞める」
「なんでやる気が続かないんやろ」
「教えても定着せえへん…」
そんな悩み、どこかで感じたことありませんか?
「人の問題」って、経営者にとって一番ややこしいし、一番エネルギーを持っていかれる部分でもありますよね。
でもこれ、実は行動科学的に見ると共通の“理由”がちゃんとあるんです。
「辞める人が多い組織」にある“3つの共通点”
行動科学の視点や実際のコーチング現場でも、「辞めたくなる環境」にはこんな特徴がよく見られます。
❶ 行動のゴールが見えない(=何が正解か分からない)
例:「とにかく自分で考えてやって」
→ え、どうなったらOK?それ、どのレベル?状態です笑
人は、自分の行動の“基準”が見えないと、不安になります。
❷ 行動のあとに「報酬」がない(または“罰”になってる)
せっかく頑張ったのにスルーされる
→ 「この職場、やってもムダやな」になる。
逆にちょっと失敗しただけで怒られる
→ 「怖くて動けないから、辞めようかな」になる。
❸ ルールが曖昧、もしくは急に変わる
「昨日と言ってることが違う」
「上司の気分で指示が変わる」
…これ、意外とありますよねー。
一貫性がないと、「どう動けばいいのか」がわからなくなって、行動の継続ができなくなります。
ABAで考える「辞めたくなる組織」とは?
行動科学では、「行動が続くには、その直後にポジティブな結果(強化子)が必要」とされています。
つまり、
- ✅ 良い行動には、すぐにちょっと嬉しいことがある
- ❌ ミスしても、次につながるチャンスがある
この仕組みがないと、人は「ここにいても自分は育たないな」って判断するんです。
じゃあどうする?辞めたくならない組織にするための3つの工夫
①「行動の見える化」をする
人は“曖昧”がストレスです。
だから、「何を・どのレベルで・どれくらいやればいいか」を、できるだけ行動ベースで見える化するのがコツ。
たとえば:
- ❌「しっかり報連相してね」
- ✅「毎朝10時までにタスク共有をチャットで送ってね」
②「褒めるハードル」を地面スレスレまで下げる
「ほめポイントが見つからない…」じゃなくて、“行動の最初の一歩”を見つけて声をかけることが大切。
例:「お、今日は出社早いね〜!」
→ それだけで“リズムを整える行動”が強化されます。
ちょっとの変化でも拾って反応すると、行動は続きます。
③「ルーティン」と「安心できる一貫性」をセットで設計する
突然の変更や曖昧なルールは、人を不安にさせます。
だからこそ、“習慣に落とせるルール”にしておくと、安心感が生まれます。
たとえば:
- 曜日でやることを固定する(毎週月曜は朝礼+相談タイム)
- 社内チャットの使い方にルールをつける(報告は〇時までに)
この“一定の安心感”が人をつなぎとめる土台になるんです。
辞めた人を責めるより、「辞めたくなる設計」を見直そう
人が辞める理由って、「その人の根性のなさ」ではなくて、
“行動が続かないようにできていた”環境の問題かもしれません。
だからこそ、やるべきは…
- 教え方を変えることでも
- 管理を厳しくすることでもなくて、
👉 “行動を続けやすい設計”に変えること。
これができると、辞める人が減るだけじゃなく、育つスピードも上がります。
最後に:まずは“ひとつの行動”だけでも変えてみよう
全部をいきなり改善しようとしなくてOKです。
まずは「この行動が続いてくれたらいいな」と思う1つを選んで、
- どんな言葉できっかけを出して
- どんな反応で強化して
- どんなルールで安心させるか
…この3つを意識するだけで、変化は生まれます。
「続けられる行動は、辞めたくない職場をつくる。」
そんな組織のあり方を、行動設計から始めてみませんか?
気軽に試してみてね〜!笑


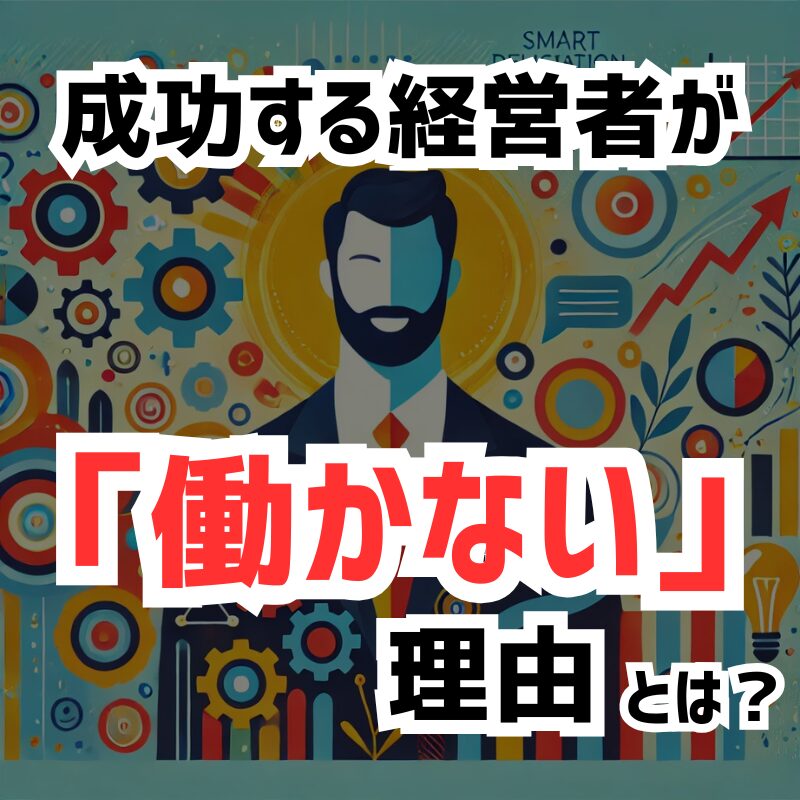
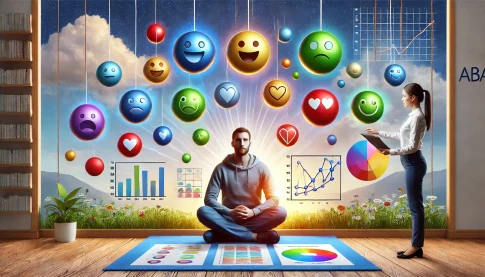








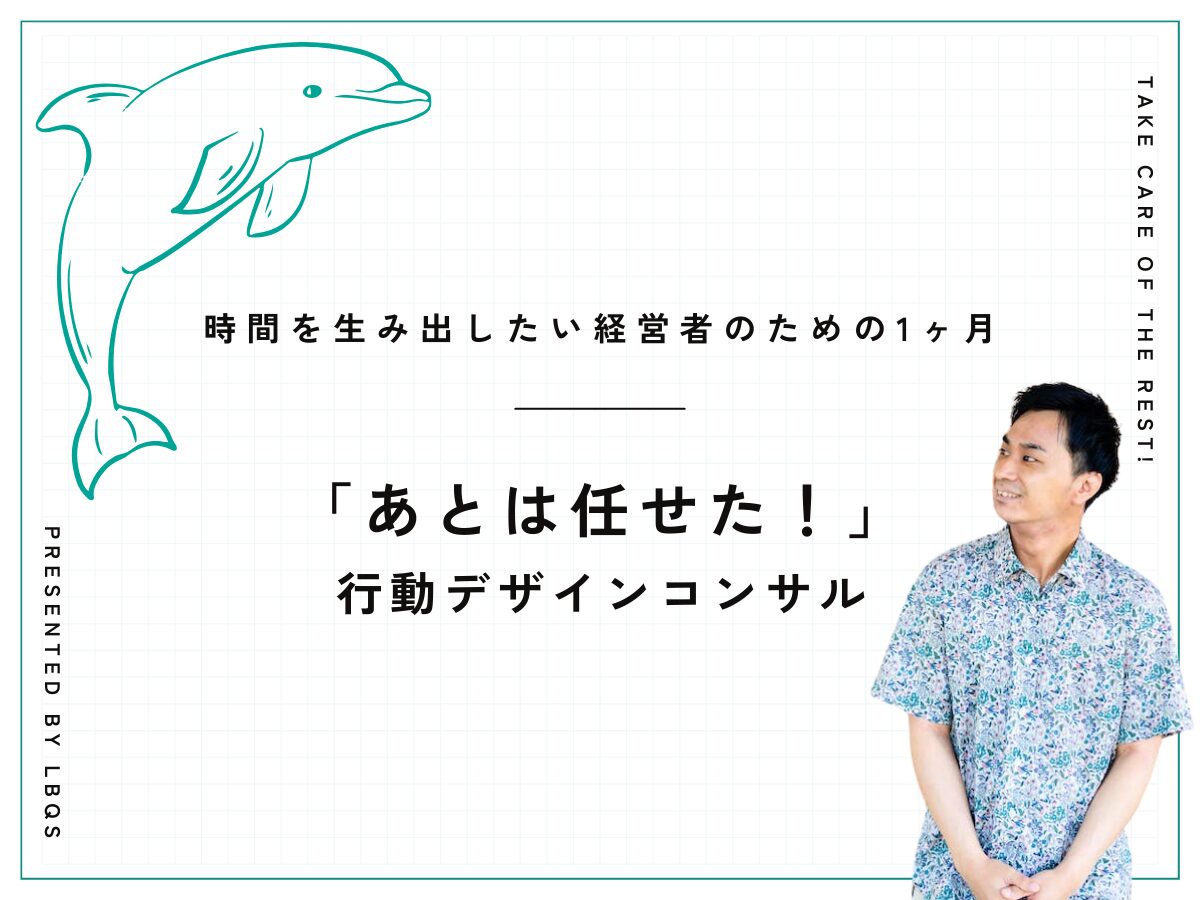
元イルカの調教師で、応用行動分析学を使った行動デザインコンサルタントの櫻井 祐弥です。