あなたは日々の仕事で、自分の態度を意識的に選んでいますか?
今回のテーマはFISH !哲学
FISH!哲学の「態度を選ぶ(Choose Your Attitude)」は、どんな状況でも自分の態度をコントロールし、より良い結果を生み出すための原則。
でも実際のところ、多くの人は環境やストレスに左右されて、無意識のうちにネガティブな態度を取ってしまうんですね。(反省しないといけない…)
ここで応用行動分析(ABA)を活用すると
「態度を選ぶ」
を実践しやすくなります。
今回の記事では、ABAの視点から態度を変える方法を解説して、日常や仕事に活かせる具体的なステップを紹介します!
態度を選ぶことの本質とは?
実は、行動定義には2種類あるんですが知ってましたか?
- 筋肉や腺の動き
- 死人にできないこと全て
この2つに当てはまることは全て「行動」としてカウントすることができます。
もちろんです、「態度」も単なる気持ちの問題ではなく、行動の一部になります。
なぜ態度は変えにくいのか?
- 習慣化された反応 → 人は過去の経験に基づき、無意識に態度を決めている。
- 環境の影響 → 仕事のプレッシャーや人間関係が、態度を左右する。
- 行動の仕組みの影響 → 周囲からのフィードバックによって、特定の態度が繰り返される。
例えば、毎朝忙しい職場に入るとき、無意識に「疲れた」「また今日も大変だ」と思う人もいますよね?(僕もそんな時期がありました笑)
でも、それは過去の経験や環境によって形成された反応なので、意識的に選ぶことができるわけです。
3. 態度の選択がもたらす影響
「態度を選ぶ」ことができると、次のような効果が生まれます。
ビジネスシーンでの影響
- リーダーの態度がチームに伝わる(ポジティブなリーダーがいると、社員のエンゲージメントが上がる)
- 顧客対応の質が向上する(接客業では、ポジティブな態度が顧客満足につながる)
リーダーの雰囲気って、チームや組織の空気感を決めますよね?
いつだったかテレビで「ディスニーランドの働く人特集」を見たんですが、上司の方が非常に雰囲気良く新人教育をされていました。(確か女性の方)
教えられている側も、過度なプレッシャーを感じる様子もなくしっかりステップを踏んで行動が変わり、お客様対応もスムーズにできている様子。
当然、夢の国ディズニーの顧客満足度は画面上でも伝わるほど笑顔がたくさん映ってました。
個人レベルでの影響
- 仕事のストレスが軽減する(ネガティブな態度は、脳のストレスホルモンを増やす)
- 人間関係が改善する(態度を変えると、相手の反応も変わる)
FISH!哲学のパイク・プレイス・フィッシュ・マーケットの店員たちは、決して楽な仕事をしているわけではありません。
でも、「態度を選ぶ」ことで、楽しみながら働き、結果的に売上も伸ばしています。
「態度を選ぶ」は、最も簡単で効果が見られる「GIVE First」の現れかと考えています。
そもそも、人も含めた動物は
快刺激には接近して、不快刺激を避ける
って修正がありますから、不快な態度をしていると周りから人がいなくなりますね笑
4. 「態度を選ぶ」を実現するABA的アプローチ
では、どうすれば態度を意識的に選べるようになるのでしょうか?ABAを活用した4つのステップを紹介します。
① 環境をデザインする
- ストレスを感じる環境を改善し、態度を選びやすくする。
- 例:「ポジティブな言葉が書かれたメモをデスクに置く」「職場の雰囲気を変えるBGMを流す」
良くも悪くも、僕たちは環境の影響を強く受けてしまいます。
ちょっと蒸し暑いとキレが悪くなりますし、愛車を擦った後のインスタライブなんかはテンションガタ落ちです。
もちろん
ネガティブな環境ではネガティブな態度が出やすいのですが、ここは起きた事実をどう解釈するかで態度を選ぶ余地が生まれます。
蒸し暑い→季節が変わってきた
愛車を擦った→人を巻き込まなくてよかった
こう思うだけでも、その後にとる「態度」を選ぶことができますね。
ですが、大切なことは「実際に態度を選んだ」という行動をとること。
行動をとることで、僕たちの行動は強く学習されます。
② 強化の原理を活用する
- 良い態度を選んだときに、自分や周囲が報酬を得られる仕組みを作る。
- 例:「笑顔で挨拶したら、相手も笑顔で返してくれる」「目標達成時に小さなご褒美を設定する」
僕たちの行動が身につくためには「結果」が重要です。
この結果を意図的に作ることで、より良い行動の頻度を上げることができます。(これを強化って言います)
この強化は、普段から意図しておくと適切に使うことができるテクニックなので「これができたら自分を褒めよう!」と頭の中に意識を残すことが重要です。
③ ルーチン化・習慣化する
- 態度を選ぶ行動を、毎日のルーチンに組み込む。
- 例:「毎朝1つポジティブなことを考える」「1日の終わりに良かったことを振り返る」
行動の頻度を増やして、徐々に日常の中に取り入れることができれば、習慣になります。
習慣は人生に影響を与えるほどの力がありますので、態度を選ぶことが習慣になれば、おそらくあなたの周りの行動にまで影響が出るレベルになっています。
④ 振り返りと改善
- 自分の態度を評価し、改善する仕組みを作る。
- 例:「日報に『今日の態度』の欄を作る」「週1回、自分の態度を振り返る」
行動に100点ってないんですね。
これは比喩的なものではなくて、普通にしてると大体80点くらいで収まります。
というのも、僕たち動物は常に試行錯誤をして行動を変えるからですね。
「もっと簡単に、楽に成果を得る方法はないか」
これを無意識に探し続けますから、より良い改善をし続けることは非常に重要です笑
なぜなら、すぐサボっちゃうから!笑
5. 時間軸で考える
「態度を選ぶ」ことがどのように定着するのかを、時間軸で見てみましょう。
短期(1週間~1ヶ月)
- 「態度を選ぶ」意識を持ち始めるだけで、周囲の反応が変わる。
- ポジティブなフィードバックを受けることで、モチベーションが上がる。
最初の第一歩は、可能な限り低いハードルで設定するとやりやすいですね。
自分で自分を褒められるような仕組みを使えば、もっと行動頻度が上がりやすいです。
中期(3ヶ月~6ヶ月)
- 自然とポジティブな態度を選べるようになり、ストレス耐性が上がる。
- 職場の雰囲気が変わり、チーム全体のモチベーションも向上する。
このタイミングになると、考え方も変化します。
思考がポジティブになったり、物事を多視点で捉えられるようになります。
長期(1年以上)
- 組織文化に影響を与え、リーダーシップや組織開発に活かせる。
- 人生全体の満足度が向上する。
周りの行動が変わり、変化を感じる時期です。
1年続けば、あとはより影響の輪を広げる段階になります。
6. まとめ
今回のまとめです。
態度を選ぶというテーマで進めてきましたが、いかがだったでしょうか?
要点まとめ
- 態度は選ぶことができるが、無意識のうちに環境に左右されていることが多い。
- ABAの視点から環境をデザインすることで、態度を選びやすくなる。
- 短期・中期・長期で、態度の選択が人生や組織の成果に影響を与える。
最初の一歩として
✅ 「今日の態度を選ぶ」ワーク
- 明日の朝、「今日はどんな態度を選ぶか」を決めてみる。
- コメント欄やSNSで「#態度を選ぶチャレンジ」と投稿!
行動に移さない限りは、僕たちが行動を身につけるのは非常に難しいです。
ぜひ、何かしらの挑戦をしてもらえたら嬉しいと思います。
行動に関す相談、組織に関する相談があれば、ぜひお声がけください。
ではまた!


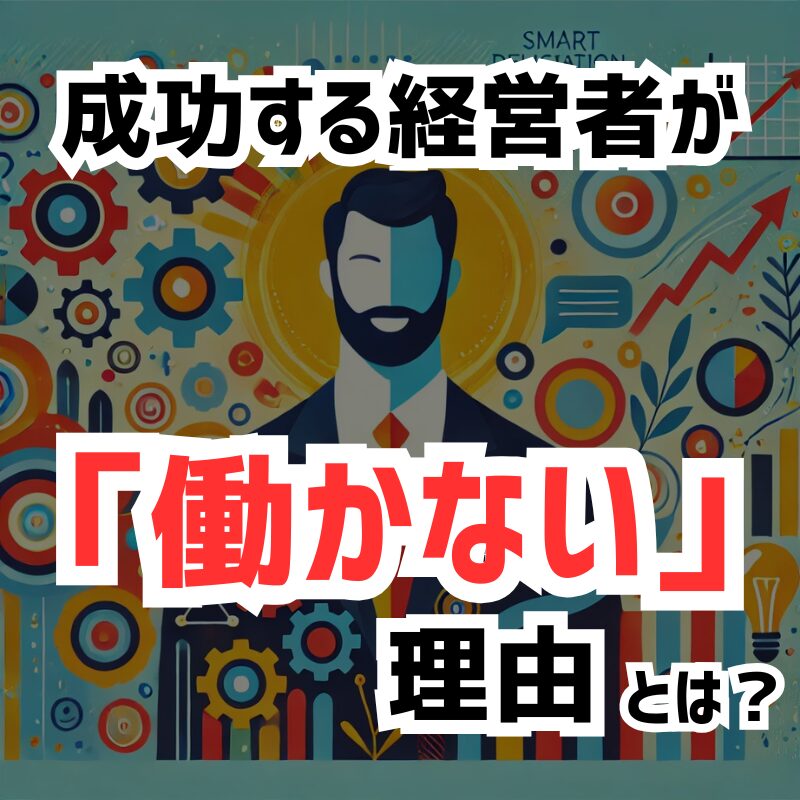
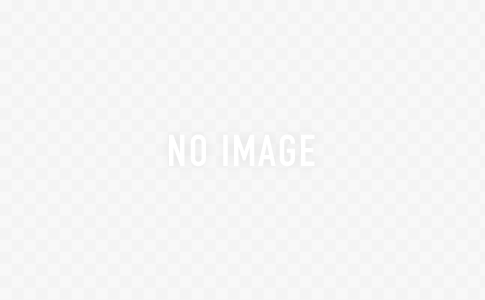




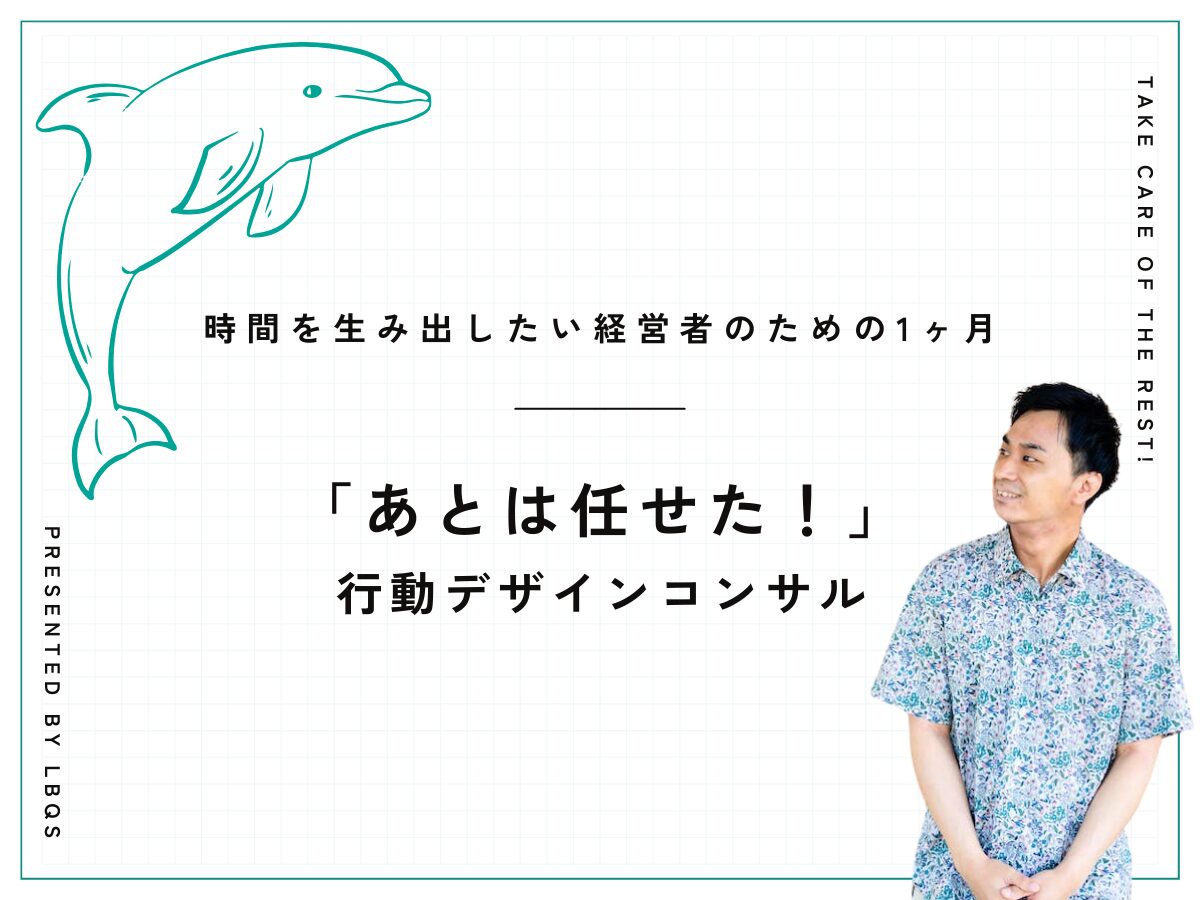
元イルカの調教師で、応用行動分析学を使った行動デザインコンサルタントの櫻井 祐弥です。